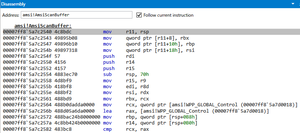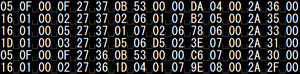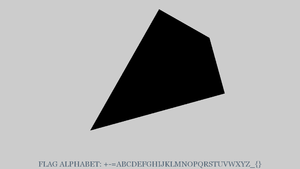セキュリティ技術者の育休
-

近況報告
SECCON CTF 2022 予選に参加しました。
-

近況報告
Azure AD導入環境に対するペネトレーションテストの資格「Certified Az Red Te...
-
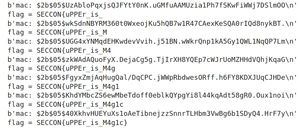
CTF
SECCON CTF 2021(Case-insensitive)
-

近況報告
SECCON CTF 2021参加報告
-
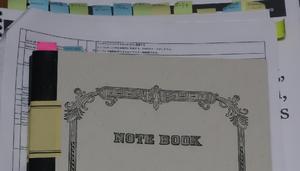
近況報告
GIAC Cloud Penetration Tester (GCPN)を取得しました
-

CTF
DEF CON CTF Qualifier 2021(qoo-or-ooo) Writeup
-
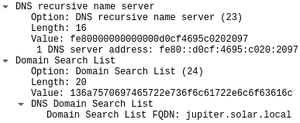
技術検証
DHCPv6 spoofingについて
-

CTF
セキュリティコンテストを開催しました。
記事を探す
SEARCH
人気記事
POPULAR